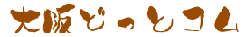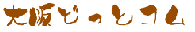��������
 �͑��݃����N�T�C�g�ł��B
�͑��݃����N�T�C�g�ł��B
�@ 1 - 10 ( 16 ���� )�@ [ / 1 2 / ���y�[�W�� ]
�������y�����X�V���F2018/09/19(Wed) 22:37 [�C���E�폜] |
|
�������y����i������Ԃ�炭�������傤�ANational Bunraku Theatre�j�́A���{���s������ɂ��錀��B4�Ԗڂ̍�������Ƃ���1984�N�ɊJ�فA�召��̌���ƓW�����Ȃǂ���Ȃ�B��z�[���ł͐��E���`������Y�Ɏw�肳��Ă���l�`��ڗ��E���y�̌����𒆐S�ɉ����║�x�Ȃǂ��s����B���z�[���ł͊���ɗ���E���ˁE�Q�ȂȂǂ̋��s�u������|���I��v���J����A�����̍�������ɂ����鍑�����|��I�������S���B�Ɨ��s���@�l���{�|�p�����U����ɂ��^�c�B �ȏ�wikipedia��� |
�≮�y���j�Ձz�X�V���F2012/01/21(Sat) 22:35 [�C���E�폜] |
|
���q���z�[���y�[�W�̊≮�y���j�Ձz�̏Љ�y�[�W�ł��B |
�ʓV�t�̗w�����X�V���F2011/10/30(Sun) 16:51 [�C���E�폜] |
|
���|�|�\������Ђ̒ʓV�t�̗w����̃y�[�W |
�ʓV�t�X�V���F2011/11/02(Wed) 23:06 [�C���E�폜] |
|
�ʓV�t�i���Ă��j�́A���{���s�Q����ɂ���V���E�E�G�̒��S���Ɍ��W�]���ł���B���̓o�^�L�`�������B�ό������Ƃ��ėL���ł���B ���݂̒ʓV�t�͓��ڂŁA1956�N�i���a31�N�j�Ɋ��������B�ʓV�t�ό�������Ёi���Ă������ATsutenkaku Kanko Co., Ltd.�j�ɂ��^�c����Ă���B�𗋐j���܂߂�������103m�i�����̂̍�����100m�j�B�v�҂́A�قړ������ɂł������É��e���r���A�����^���[�Ȃǂ��肪�������������B���݂��{�H�����͉̂����g�ł���B �u�ʓV�t�v�Ƃ́A�u�V�ɒʂ��鍂�������v�Ƃ����Ӗ��ŁA���������͖̂��������̎�w�ҁA�����x�ł���B�E�E�E�E�E �ȏ�wikipedia��� |
�m���V�c�ˌÕ��i���(�R)�Õ��j�b��ό��K�C�h�X�V���F2011/10/05(Wed) 17:18 [�C���E�폜] |
|
�ȉ�wikipedia�u���ˌÕ��v�����p���܂����B ���ˌÕ��i���������傤���ӂ�A���Õ��A��R�Õ��Ƃ��j�́A���{��s����咬�ɑ��݂�����{�ő�̑O����~���B���͂̌Õ��Ƌ��ɕS�㒹�Õ��Q���\�����Ă���B���ʐς����E�ő�ł���Ƃ����B �{�����ɂ��m���V�c�̗˕�Ǝ��肳��Ă���A�S�㒹�������ˁi�����݂݂̂͂�̂Ȃ��݂̂������j�Ƃ̗ˍ����^�����Ă���B��ʓI�ɂ͐m���V�c�ˁi�ɂ�Ƃ��Ă�̂���傤�j�܂��͐m����ˁi�ɂ�Ƃ�����傤�j�ƌĂ��B |
�痘�x���~�Ձb��ό��K�C�h�X�V���F2011/10/05(Wed) 17:15 [�C���E�폜] |
|
�ȉ�wikipedia�́u�痘�x�v������p���܂����B �痘�x�i����̂肫�イ ����肫�イ�A��i2�N�i1522�N�j-�V��19�N2��28���i1591�N4��21���j�j�́A�퍑���ォ����y���R����ɂ����Ă̏��l�A���l�B ��ђ��i�����̒��j�̊����҂Ƃ��Ēm����B�����Ƃ��̂�����B�܂��A����@�v�E�Óc�@�y�Ƌ��ɒ����̓V���O�@���Ə̂���ꂽ�B |
�Ȃ�O�����h�Ԍ��X�V���F2011/09/15(Thu) 16:23 [�C���E�폜] |
|
�Ȃ�O�����h�Ԍ��i�Ȃ�O�����h�����j�́A���{���s������ɂ���A�悵���ƃN���G�C�e�B�u�E�G�[�W�F���V�[���^�c���邨���E�쌀���̌���i2007�N9���܂ŋg�{���Ƃ��^�c���Ă����j�B����NGK�i�G�k�W�[�P�[�j�B�L���b�`�R�s�[�́u���̓a���v�B �ȏ�wikipedia��� |
�K�m�@�|�@����w�X�V���F2011/09/14(Wed) 23:34 [�C���E�폜] |
|
����w�z�[���y�[�W�̃T�C�g���̃y�[�W�ł��B �ȉ���wikipedia�����p �K�m�i�Ă����キ�j�Ƃ́A���w�ҁE��҂Ƃ��Ēm���鏏���^�����]�ˎ������ɑ��E�D��ɊJ�������w�̎��m�B�����ɂ͓K�X�֏m�i�Ă��Ă��������キ�j�Ƃ����B�܂��A�K�X�m�Ƃ��̂����B�����^���̍��ł���u�K�X�ցv�����̗R���B �������疾���ېV�ɂ����Ċ����l�ނ𑽂��y�o���A���݂̑���w�ƌc��`�m��w�̌�����1�ƂȂ����B ��Ȗ剺�� �������i�c��`�m���A���R�R�㑍�āA���R�R��w�Z�Z���j ��Ҋ��i���R�R�㑍�āj �Γc�p�g�i�j�݁A�C�������m�j ���c�ۑ��i���b�A��2��c��`�m���j �咹�\��i�ڈ��a���̗��R��s�B������w�K�@�@���B�������g�B�j�݁j �呺�v���Y�i�u���c�Lj��v�ƌ������œ��m�B���{�ߑ㗤�R��n�݁j ���{���g�i�c��`�m����m���A�����Ә��w�Z�n���ҁj ����햯�i���{�ԏ\���Џ��㑍�فB���݁j ��˗ǐ�i����ƁE��ˎ����̑]�c���j �˒˕��C�i�C�R�R�㑍�āj ���^��ցi���V�@�c���A�����Ȉ㖱�ǒ��j ���{�����i�Ⴍ���Ĉ����̑卖�ŏ��Y�j �Ԗ[�`���i�q�݁A�����ږ⊯�j ����@�g�i�c��`�m�̑n���ҁj ����H�i�O���w�ɂ̑n���ҁj ���̑����� |
�V�����������X�V���F2011/09/23(Fri) 15:26 [�C���E�폜] |
|
�V�����������̃z�[���y�[�W |